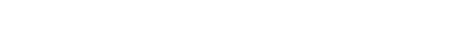小冊子 think transplant Vol.27
臓器提供者の主治医の手記

限られた時間をどのように過ごすかをご家族とともに一生懸命考えています。
主治医として関わった脳死下臓器提供
ある冬の午後、私が勤める救命救急センターに40歳代の男性が搬送されてきました。事務所で仕事中、急に倒れてそのまま心肺停止となったのです。救急隊により懸命の蘇生処置が施され、そこで心拍再開したのちに搬送されました。
検査の結果、最も重症のくも膜下出血でした。昏睡状態で血圧も不安定なため手術ができず、まずは点滴治療を行いながら回復を待つことになりました。しかしその後も改善の兆しはみられず4日が経過しました。手足をまったく動かさず呼吸も人工呼吸器に頼り切った状態です。主治医の私はご家族と相談し、脳の機能を確かめる検査を行いました。脳波検査は脳の活動が完全に停止しているという結果でした。「脳死とされうる状態」と診断されました。今後あらゆる治療を行ったとしても救命が困難であること、そして臓器提供という選択肢があることをお話しました。奥様は涙を浮かべながら、じっと説明を聞いておられました。主治医にとって、ご家族に回復の見込みがないことを告げるのはこの上なく無念なことです。しかしそれ以上に、ご家族にとって病状を受け入れることは大変つらいものだったと思います。
奥様より「臓器提供します」という申し出があったのは、それから2日後のことでした。「もし主人が移植を受けて助かるような病気なら、ぜひ移植を受けたいと言うと思います。でもそれが叶わないのなら、せめて移植を待っている人に主人の臓器を使ってほしい」と脳死下での臓器提供を希望されました。法的脳死判定を経て死亡宣告ののち臓器摘出手術が行われ、それぞれの臓器は移植手術を待つ全国の患者さんのもとへ無事に届けられました。
お見送りのとき、奥様はわれわれに向かって深々と頭をさげ「ありがとうございました」とおっしゃいました。その言葉は、救命できなかった無力感でいっぱいの私の心に重く響き、ただただ涙が止まりませんでした。
提供から1年後
臓器提供から1年あまり経過した頃、私は臓器移植コーディネーターと共にドナーのお宅を訪問しました。私はずっとご家族の様子が気になっていましたが、その反面直接お会いすることはとても気が重かったのです。入院中つらい話ばかりした私の顔を見るのはいつまでたっても嫌なんじゃないだろうか、臓器提供を決断されたことを今も悩んだり後悔されたりしていないか、と不安でいっぱいでした。
奥様は、私の不安を吹き飛ばすかのような笑顔で迎えて下さいました。居間には仏壇があり、たくさんの写真や、思い出の品々が並べてありました。臓器提供をしたことは友人や知人にも話されており、「すごいね」「いいことをしたね」と言われ、とても嬉しかったそうです。そして「当時、臓器提供の話をしてもらったことは本当に良かった。あのとき言われなかったら臓器提供なんて考えなかったし、それに主人の臓器が誰かの役に立つのならとても嬉しい。灰になるくらいなら多くの人の役に立ててもらい、そしてどこかで生きていてほしい」と言って下さいました。悲しみを乗り越え、今を前向きに生きているご家族の様子をみて、私は心から安心することができました。と同時に私自身がこれまでずっと心に抱いていた、救命できなかったことへの無力感やご家族に対する申し訳なさ、そんな気持ちが、すっと楽になるような不思議な感覚がしたのです。移植医療は臓器を提供するご家族にとって、そしてさらには治療に携わった医療者にとっても、グリーフケアとしての力を持っているような気がしました。
臓器移植は究極のチーム医療
私は、臓器移植というものは救急領域とまったく別世界で行われているものだと思っていました。しかしこの経験を通じて、救急の現場が移植医療のまさにスタート地点にあることを知りました。小さな説明室で患者さんのご家族と向きあい何度も話をし、そのなかで臓器提供という選択がなされた瞬間から「命のリレー」が始まります。患者さんの治療を担当する主治医、脳死判定を行う専門の医師団、ドナーやそのご家族をケアする看護師、手術室や検査を担当するスタッフ、病院を陰で支える事務職員、摘出された臓器を安全確実に搬送するスタッフ、さらに移植を受ける患者さんを治療する移植チーム、そしてその全てを統括し手続きがスムーズに行われるように調整する臓器移植コーディネーター…。本当に多くの人が、その尊い想いをつなぐために、職種をこえて地域をこえて、一つの目標にむかって走り出すのです。それはまさに究極のチーム医療と言えるでしょう。
救急の現場における終末期医療
「終末期医療」と聞いてどのような状況を想像されるでしょうか?多くは癌の末期などにおける、来たるべき死に備えた治療法の選択、つまりは痛みの緩和や延命治療について思い浮かべるでしょう。“最期のとき”まで少し余裕がある場合は、残された時間をどのように過ごし、そして最期をどう迎えるか、ご本人やご家族がじっくりと考えてその準備をすることができます。しかし突然の急病・ケガから命の危険が差し迫っている救急の現場においても「終末期」という考え方があるのです。
われわれ救急医は、常に目の前の患者さんに対して全力を注ぎ、その命を助けることが使命です。しかし時には、最善と思われる治療を尽くしてもどうしても救えない命に直面することがあります。無力感に苛まれながらも、救急医は消えゆく命を目の当たりにして、ご家族の悲嘆に暮れる気持ちをできるだけくみ取り、限られた時間をどのように過ごすかをご家族とともに一生懸命考えています。そのなかで臓器提供についてのお気持ちを聞かせていただくことがあります。ご家族にとって、とてもつらい話になるかもしれません。それでも敢えて臓器提供についてお聞きするのには理由があります。それは、もし患者さんご自身あるいはご家族が「臓器提供をしてもいい」と考えておられた場合、その最期の想いを叶えたいと考えるからです。そしてそのお気持ちについて伺える時間はとても限られているのです。臓器移植によって助かるのはもちろん移植を受ける患者さんですが、私は主治医としての経験を通じて、ドナーのご家族が臓器提供という選択をしたことを誇りに思い、そしてそれを生きる糧としておられることを知りました。大切な方を失う深い悲しみのなかで、その寂しさを少しでも癒せる力が移植医療にあるとすれば、それを伝えていくことも救急医が担うことのできる役割なのかもしれません。